さて、謎のお菓子、「21世紀のパップラドンカルメ」こと「ハルヴァ」を求める記事の第二弾。 米原さんの「あのハルヴァ」かどうかはともかく、これをきっかけに美味しいハルヴァなるお菓子を食べたく思った私は、あれ以降何かにつけてハルヴァを探すようになりました。
都内のお菓子屋でもレストランでも、とにかく「ハルヴァ」を出しているところはないかとさがしまくったところ、どうにか一軒のお店を見つけました。小伝馬町にあるイラン系輸入食材店
「DARVISH SHOP(ダルビッシュ ショップ)」です。
小伝馬町駅から徒歩5分くらいの、8~10畳くらいのちいさなお店。 中東な食材をいろいろ置いています。 ここはイランから来た人が故郷の食材を求めにくるお店でもあるらしく、ここに置いてあるハルヴァは現地人も「これこれ」というものらしいです。
米原さんのあのエッセイでのハルヴァは、当時ソ連にいた友達からのおすそわけだということで、恐らくイランのそれとは違うとは思うのですが、何事にもあたってみるのは大事です。 とるものもとりあえず行って来ました。
入店すると、おじさんがデーツをくれます。 すげえうまいです。デーツなんですが煮豆…紫花豆の甘煮みたいな味と食感で妙に懐かしい味がします。タネがでかいので注意。
購入して帰還!
そして、そこで買ったのがこれ! お値段は200gで350円ほど。 意外と安い。 ピスタチオとピーナッツのハルヴァ!


「Tahini Halva」と明示されてます。 Tahini というのはゴマペーストをベースにした、東アジア~中東で好まれている調味料というか、日本で言う味噌みたいな基本食材のようです。
つまり「Tahini でつくったハルヴァ」だということなわけで「じゃあ“ハルヴァ”って……」と、ハルヴァがさらに上の概念であることを再確認します。 要はもう、甘いお菓子みたいな大ざっぱな感覚に近いんじゃないかと類推しちゃいます。

中はこんな感じ。 ナイフでスライスして食べる模様。 ていうかこの厚みでは、パッケージの写真のような横に薄いスライスの上にナッツが乗ってる感じにはなりません。 むしろ羊羹のように縦長な切り付けに。 盛り付け例の不一致は海外パッケージあるあるですね。

油分たっぷりのしっとりした固形物。 たぶん暖めるとドロドロになる系。 ナイフを入れた手触りにはザクザクという感じもあったので、たくさんの砂糖やナッツを砕いたものなどが入っているのでしょう。
最初の一切れだったからかもしれませんが、綺麗な直方体にスライスするのは中々難しいです。 ボロッとしてしまいます。 ともあれなんとか切り出せました。
テイスティング:「うん。ゴマ。ゴマだ。Tahini だ」

そして肝心のお味なんですが…
非常にゴマです。 ゴマペーストです。 甘いゴマペースト。 それに、複雑な香辛料の香りが鼻を抜けていきます。 とてもエスニック。
私としては「まあ、美味しい」って感じ。 濃い紅茶にばっちり合います。 うんと甘いしオイリーなので、バクバク食べるというよりは完全に「お茶請け」ですね。 コーヒースプーンでちまちま舐めていく感じです。
中東風の香辛料の異文化な感じが楽しいのと、ペースト状なのに口に入れるとナッツと砂糖のシャリシャリした歯ごたえが心地よいです。 いわゆる「普通に美味しい」て奴ですね。(香辛料とかゴマの好き嫌いはクリティカルに影響すると思いますが)
食感は「黄な粉ペーストにゴマの裏ごしを混ぜてうんと甘くした食感」です。 ねっとりしつつも粉っぽさがあり、その粉っぽさをゴマの油で伸ばしている……。
って、ちょっと待て。 それもう「Tahiniのお菓子全般に言えること」ってことでは(笑)。
これは「ハルヴァ」的な「Tahini のお菓子」だ
乱暴な言い方になってしまいますが、このハルヴァは、Tahini を粉食材で固めて香りをつけた「Tahini の食べ方の1つ」の様に思います。
Tahini について色々調べてみたところ、これ、やっぱり日本で言う「味噌」に立ち位置がとても近いです。 基本的な食料であり調味料である万能食。 ガチで油っこいところは日本とは違いますが。
パンだったりスープだったり、色々なものに Tahini を入れて味を整えているみたいです。 古き日本の大豆文化ならぬゴマによる「Tahini 文化」ですね。
もしかしたら「ハルヴァ」っていうのは、そういう「油分の多い食材のペーストを固めて甘味と香り付けしたお菓子」という概念なのではと、類推を1つ押し進めてみたり。
そして、その概念の中の1つ(といってもメジャー)として Tahini のハルヴァがあると。 なるほどそういう風に解釈すれば良さそうです。
家庭料理としての「Tahini ハルヴァ」
これって現地の人の家庭の味なんでしょうね。 Youtube等で動画をチェックしましたが、やっぱりそんな家庭料理な感じでした。 この動画だと粉ミルクも使ってます。
すごい簡単に作れそう。 ていうかこの動画の食べるところで、なかなかピスタチオをフォークで刺せないところがちょっとかわいい。
世界的にはハルヴァの主力は Tahini っぽい……
食べてみて「ちょっと違うな」と思い、色々と検索の網を広げてみたんですが、すると意外なことに、ヒットするハルヴァの殆どがTahini のハルヴァです。
ロシア(というか旧ソ連圏)の方でも Tahini ハルヴァは作られてますし、「あるか無いか」の話だけで言えばスペインの方でもそのレシピはあります。
ていうか、Tahini 文化圏がそれだけ広いってことですよね。 Tahini あるところに Tahini ハルヴァありというわけです。
米原さんの食べたハルヴァにはTahini どころかゴマっぽい記述すらなかったので、これは違うんだろうなあと思いますが、むしろ米原さんの食べたハルヴァの方が少数派だったのかもしれません。 そして、Tahini 以外のハルヴァのレシピも色々あるんだろうなあと。
Wikipediaによれば、ハルヴァの起源は古代のイラン近辺だったということで、じゃあ本式は Tahini なのかなと思いつつも、逆に「わざわざ Tahini Halva って呼ぶからには大元の Halva もあるんだろう」とも考えられます。
イランでも Tahini 以外に……それこそ「無印の Halva」があるのかもしれませんよね。
次なるハルヴァに向かって……!
私が米原さんのエッセイで魅せられた「あのハルヴァ」は、ここまでペースト状ではなく、香ばしくて、ゴマでもないものでした。
「あのハルヴァ」を100%求めるのは無理だとは思いますが、こうして興味を持った上は、もっと調べて色々なハルヴァに挑戦して「これが俺的な“あのハルヴァ”だ!」と言えるものを探し出したいと思います。
今回はちょっと違いましたが、逆に言えば世界の主力ハルヴァである「Tahini 文化圏のハルヴァは違う」と結論付けられたことは、かなりの割合を割愛できたとも言え、一応の前進ではあるでしょう。
次は Tahini でないハルヴァに挑戦してみることにします。
……では、また次のハルヴァの記事に続くことを願って…!
【関連記事】

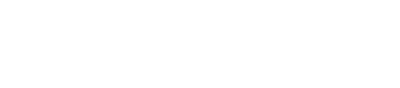


よく読まれている記事